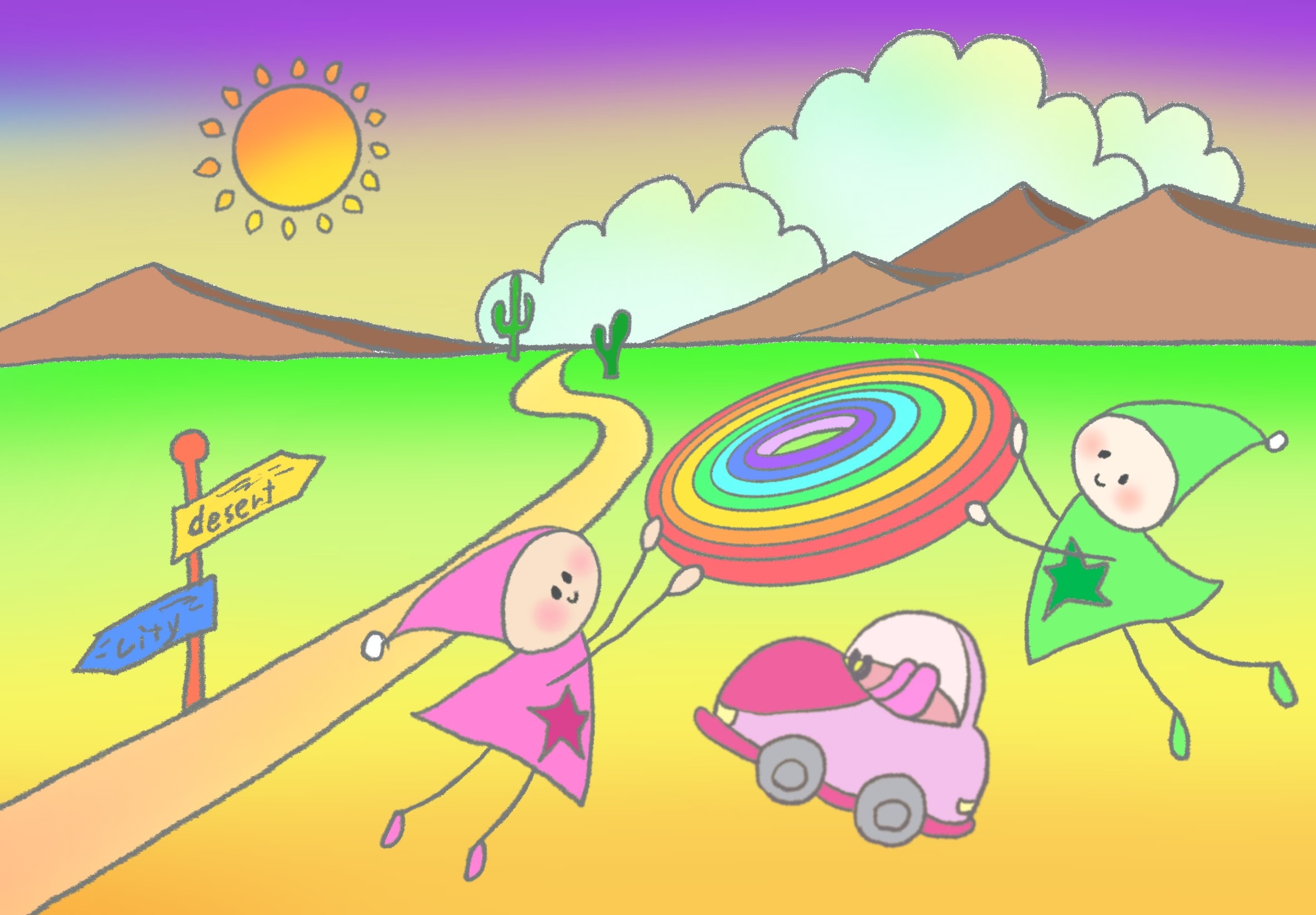
ルリスが新しいタオルを渡してくれた。それで頭をふき、給水タンクを持ってレグルスに戻った。
「雲でレグルスを包まないと、泥沼を抜けられないね。まあ、雲自体には困らなさそうだけど」
プレトがそう言って空を見ると、ふわん、ふわんと、雲が次々と落ちてきている。レインキャニオンから戻ってから、再びオルタニング現象が起こりはじめたのだ。朝といい、今といい、タイミングがとても良い。
……もしかして、輝く人が助けてくれているのかな?
確認する術はないが、誰かの力にしろ、ただの自然現象にしろ、ありがたく使わせてもらうことにした。ルリスと協力して雲を集め、固定し、レグルスを包んでいった。友人の愛車はまたファンタジーな装いになった。
「これまでに遭遇した危険以外にも、何かあるかもしれないし……早速だけど、昨日避難した住宅街まで戻るのはどうかな? あそこなら安全だろうし、今日中に着くよ」と、プレト。
「そうしよう。虹は採取したから、レインキャニオンにもう用はないもんね」
二人は最後に一度だけ、レインキャニオンを見下ろした。
「ねえ、シャモジちゃんが登ってきてるよ!」と、ルリス。
谷間で行動を共にしていた危険植物が、ゆっくりと岩壁を登ってきている。プレトたちがくくりつけておいたロープはなくなっていた。飛行物体と戦っている間に、ちぎれてどこかに飛んでいったのだろう。
「あんなに暴れていたのに、特にダメージはなさそうだね。随分と丈夫だなあ。動画撮っておこうっと」
友人はそう言って、携帯電話のカメラを向けた。
「あれは本当に植物なの? やたらと軽くて頑丈で、崖も登れて……細胞壁とかどうなっているんだろう。研究したら面白そうだな」
「撮れた! 行こうか、シャモジちゃんが登ってきたら、今のわたしたち、襲われちゃうから」
二人は急いでレグルスに乗り込み、森に突入した。泥沼地帯からぜんまい状のツタが顔を出していたが、雲のおかげでこちらには全く反応しなかった。
「普通の雲と、電気を含ませた雲をうまく使い分けられれば……なんとか敵襲をやりすごせないかな」
プレトがブツブツとひとりごちていると、思いのほか、あっさりと森を抜け出すことができた。
「追っ手が来るかもしれないから、ガンガン飛ばすね!」
「お願いしますっ」
言いきるか否かのタイミングで、身体が座席に押しつけられた。ルリスがアクセルを踏みきっている。これなら誰にも追いつかれないだろうと思っていると、本当に追いつかれることなく、住宅街まで戻ることができた。というか、敵自体を見かけなかった。プレトが拍子抜けしていると、ルリスが言った。
「わたしたちが、あの飛行物体から逃げられると思っていなかったのかもね。追っ手を準備していなかったのかも。向こうは混乱しているのかな」
「普通はアレから逃げられないだろうからね……今日の移動はここまでにしよう、夕方だし」
「賛成。さすがにもう疲れたしね。今日はレインキャニオンで頑張ったんだから、もう充分だよ」
陽が昇ると同時に起きてから、ずっと動きっぱなしだった。二人とも疲労困ぱいだ。まだ寝るには早すぎるが、そんなことはどうでもいい。プレトとルリスはそれぞれ寝袋に身体をねじこんだ。プレトは目を閉じたまま言った。「ドクププに刺されてから毎日、夕方になると発熱していたけど、今はなんともないよ」
「虹が効いたんだね」ルリスの嬉しそうな声が聞こえた。「わたしはクライノートに投稿してから寝ようかな。レインキャニオンでの出来事をみんなに知ってもらわないと!」
「うん……」
プレトの意識は、夢の中へダイブした。
「ワンワン! ワンワン!」「ちょっと、だめだよ!」
プレトは目を覚ました。なにやら騒がしい。窓に目を向けると、視界がクリアだった。レグルスを包んでいた雲が、寝ている間にすべて霧散していたのだ。虫取りを教えたあの少年が、公園で犬の散歩をしているのが見えた。
「おはよう。こんな早くからどうしたの?」
レグルスから降りて、少年に声をかけた。
「やっぱり師匠が乗ってるレグルスだったんだ! ねえ、こいつが言うことを聞かないんだよ。『わんにゃん好き好きウィーク』の間に、保健所から引き取ったんだ。飼いはじめたばっかりなんだよ」
少年は、親指で犬を指さして言った。
「そういうことか。舐められないように気をつけないとね」
「むーん……」
少年は困ったような顔をしたが、口元に笑みを浮かべている。犬がかわいいのだろう。
「そうだ。母ちゃんの携帯でクライノート見たけど、師匠は遠くから来たの? すごい冒険してるよね」
「まあ、いろいろあってね。都会から来たんだ。友人が起きたら出発するよ。家に帰るんだ」
「もう行っちゃうんだ」
少年はそう言うと、唐突にキッズ携帯の番号を教えてくれた。
「知らない人に教えちゃだめだってば……」
「師匠はもう知ってる人だし、弱そうだし、大丈夫……」
少年は一度うつむき、足元にじゃれつく犬を見たあと、さらに言った。
「ねえ、悪いやつが追いかけてくるんでしょ? これを言ってもいいのかわかんないけど、あっちの方に進むと、砂漠に行けるんだ。慣れてる人しか通らないから、敵はあんまり来ないかも」
「砂漠……そうか、その手があったか」
「ぼくの父ちゃんが、砂漠にも小さい街があるって言ってた」
「へえ、そうなんだ。いい情報、ありがとう……あのさ、この辺ってホームセンターある?」
「ホームセンター? それならこっち。気をつけて帰ってね」
少年は指をさしたまま心配そうに言った。
「ありがとう。レグルスにいるお姉さんね、すっごく操縦がうまいんだ。だから大丈夫」
「うん……ぼく、もう帰らなきゃ」
少年が名残惜しそうにしていたので、プレトは「いつでも連絡できるから」と言って、家へ帰るよう促した。
「ズボン破けてて面白いねー!」
彼はそう言いながら手を振り、犬と一緒に帰っていった。そうだ、ジャージの右脚が肉塊に食い破られたままだった。レグルスに戻ると、ちょうどルリスが起きてきたので、少年が砂漠のある方向を教えてくれたことを話した。ルリスは何度かうなづいて言った。
「砂漠かあ。じつは、わたしもそのルートで帰った方がいいのかなって思っていたの」
二人は携帯食料で朝食を済ませると、ひとまずホームセンターに立ち寄った。
「家庭用発電機、この機会に買おうと思ってさ。もちろん自腹でね。雷雲も作れるし、なにかと使えそうだし、前から欲しかったし」
「ふふふ、前から欲しかったんだ? レグルスに積めるかな」
ルリスがおかしそうに笑って言った。
駐車場に戻ると、プレトは友人の愛車の前でうなだれてしまった。
「積めない……スペースがない……」
ピンクのレグルスの中は、もうぎゅうぎゅう詰めだった。
「うーん……こうしたらどうかな」
ルリスはそう言うと、ハロの虹をレグルスの天井に乗せた。アウトドア用のロープでボディごとぐるぐるに巻き、固定する。
「おお、これならスペースが空いて発電機を積めるけど……いいの? 見栄え的に」
ピンクのレグルスの上に、パステルカラーの大きなバームクーヘンが乗ったような外見になってしまった。特殊なコンセプトのアート作品のようにも見える。
「そんなの、気にしていられないよ」
友人がにんまりしながら答えた。発電機を積みこみ、砂漠へ向かいながらクライノートをチェックすると、昨日のルリスの投稿にたくさんのコメントが寄せられていた。悪口も多かったが、称賛や応援、無事に帰ることを願う声の方がはるかに多い。
「採取の様子に興味を持っている人が多いみたいだよ」
プレトは、操縦しているルリスに話しかけた。
「虹を採るところなんて見る機会ないもんね。手元に来るのはパラライトアルミニウムになってからだし」
「英雄扱いしてくれている人もいるよ」
「光栄だね! みんなのためにも、ちゃんと帰らないと」
「うん」
「どうしたの?」
「いやー、所長の悪口をクライノートに上げまくったから、帰りづらい気もしてきた……」
「あー……」
ルリスが口をへの字に曲げた。そのとき、プレトの携帯電話にチユリさんから着信が入った。ルリスにも聞こえる設定にして電話に出る。
「クライノート見たわよ! 採取の成功おめでとう!」
上司の声が弾んでいる。
「あ、チェックしていたんですか」なんだか恥ずかしかった。「今、帰り道なんですけど、所長の悪口を投稿しまくったから帰りづらいなって、友人と話していたところなんです」
「ああ、それなら大丈夫。あなたたちがSNSを始めてから、所長は研究所に全く顔を出してないの」
「え!」
「もう、取り巻き以外には嫌われてるんじゃないかしら。もともと人望もなかったし。あの人も終わりかしらね。そういえば、部長補佐も出勤していないわ」
「私にもここ数日、連絡は来ていないです」
そういえば、サマーブロッサムを採取するよう指示されてから音沙汰がない。密林ではケーゲルの罠に嵌められたから、こちらからも全く連絡をしていなかった。
「どうしたのかしらね。何かあったのかしら」
なんだか気味が悪い。権力者の考えること行うことは、いつも不気味だ。窓の外にふと視線を動かすと、風になびく木の種類が変わってきたのが分かった。いよいよ砂漠が近付いたようだ。
(第56話につづく)

コメントを書く