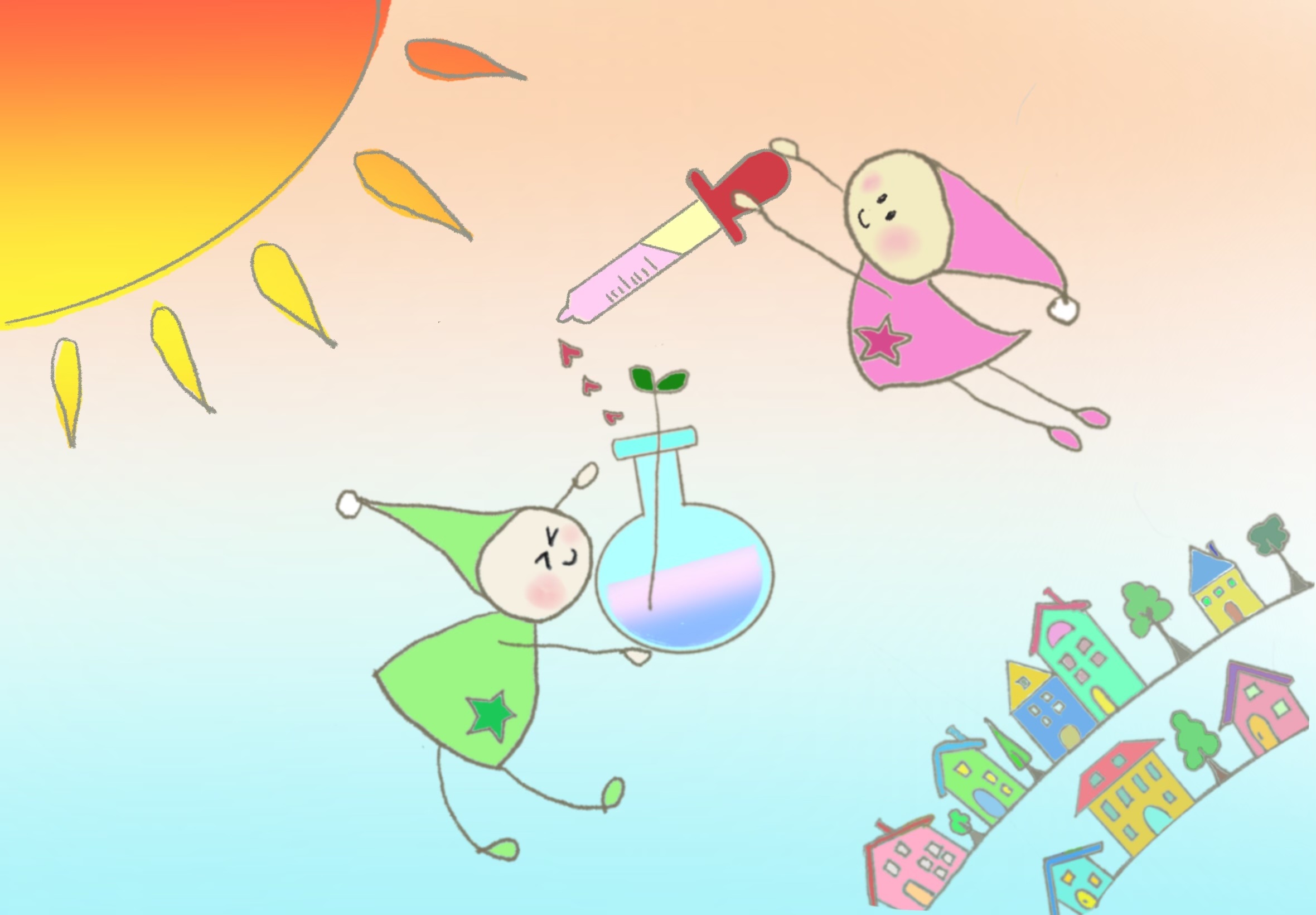
プレトはレグルスで職場に向かいながら、これから起こりそうな展開を予測する。
プライドの高い所長に、苦情の申し立てをするのだ。怒鳴られるだろうか、なじられるだろうか。考えただけでつらい。
職場に着くなり、チユリさんが駆け寄ってきた。所長がいるから話し合いができるだろうと、わざわざ伝えに来てくれたのだ。
「大丈夫だからね、終わったら話、聞くからね」
チユリさんはそう言って、プレトの背中をぽんと叩いてくれた。チユリさんが所長になればいいのにと本気で思った。寝癖も撫でつけてくれたが、チユリさんが笑っていたので、きちんと直らなかったようだ。
所長とは内線電話でアポをとり、午前中のうちに会うことになった。胃がキリキリするのを感じた。
「失礼いたします」
プレトが所長室に入ると、所長はデスクの向こうにどっしりと腰を下ろして構えていた。
「どうぞ」
所長がパソコンの画面から目を離さずに口を開いた。 プレトは両手を固く握りしめた。部屋に入ってドアを閉めると、勇気を振り絞って口を開いた。
「昨日、命令書が届いたのですが、あまりに突然のことですので、応じることはできかねます。虹の採取は辞退させていただけませんか」
所長はしばらく黙っていたが、やがて静かに言った。
「そうはいかん。君も知っているだろう。パラライトアルミニウムの枯渇問題が深刻なんだ」
「パラライトアルミニウムの枯渇問題は、本当に起こっていることなのですか。あんなに効率がいい資源なのに、枯渇するなんて、とても信じられません」
「君はニュースを知らないのか。雨季に雨が降らず、虹が出なかったんだ。足りなくなるのも無理はない」
所長は冷たく答える。 プレトは、さらに勇気を振り絞って質問した。
「虹が出ない年は、これまでも何度もあったはずです。でも、枯渇が心配されたことは一度もありませんでした」
「今年は例年より、パラライトアルミニウムの消費が激しいんだ」
「レグルスに必要なパラライトアルミニウムは数滴だけです。国民全員が毎日利用しても、消費量は問題ないはずです。マスコミが視聴率稼ぎのために、意味もなく騒ぎ立てているだけに思えるのですが」
所長は何も答えなかった。話し合う気など最初から全くなさそうだ。 だがプレトは、納得できないまま引き下がるのはご免だと思い、最も疑問に思っていることを問いただした。
「なぜ私がレインキャニオンに行かなければならないのですか。虹の採取なら、採取チームに命令するのが筋だと思います」
「君みたいな研究チームの人間にも、採取を経験させた方がいいと判断したんだ」
「だからといって、なぜ私1人で行かなければならないのでしょうか」
「他の者は皆、忙しいからだ。君は若いのだから、レインキャニオンに行くのも良い経験になるだろう」
「だけど、1人でレインキャニオンに行くのは余りにも危険すぎます」
プレトがそう言ったとき、所長はとうとう怒りをあらわにした。
「君は命令に逆らうのか。命令書は私と法務省の連名になっているはずだ。逆らうなら、この職を失うだけでは済まされない。君の両親は、他地域の研究所に勤めているそうだな」
プレトは何も言えなかった。 レインキャニオンに行くのは嫌だったが、家族が巻き込まれるのはもっと嫌だったからだ。
プレトは所長室から出た。とぼとぼと廊下を歩く。 気力も体力も全て使い果たしてしまった。所長の言い分はめちゃくちゃに思えた。
枯渇問題も信憑性がないし、仕事量はみんな同じなのだから、プレトだけ暇なんてことはない。そもそも虹の採取は、プロである採取チームがやった方がいいに決まっている。しまいには両親を人質に取ろうとするなんて…… 余りにも常軌を逸している。
プレトがそう思った瞬間、不意にある過去の出来事を思い出した。
今から3ヶ月ほど前のことだ。その頃のプレトは、休日になると必ず、趣味の研究を職場で行っていた。 ある目的に使いたい溶液を作っていたのだ。
自宅にある道具では1度にたくさん作ることができなかったので、職場の設備を拝借していた。それ自体、日常茶飯事で誰もが行っていることなので、特に問題ではなかった。
本当はただその溶液を作れさえすればよかったのだが、時間が経つに連れ、どんどん好奇心が湧いてきて、自作の溶液と、研究所に保管された様々な溶液の成分との比較を始めた。
すると、あることに気が付いたのだ。
虹からパラライトアルミニウムを抽出する際に、どうしても必要な溶液がある。それをラピス溶液というのだが、そのラピス溶液とプレトの自作した溶液の成分が、まったく同じだったのだ。
ラピス溶液は、ラピスラズリなどの宝石が主な原料になっていて、虹にかけることで化学反応が起きる。それによってパラライトアルミニウムが抽出できる仕組みなのだ。ラピス溶液は材料も貴重で、作るには高度な技術が必要だと言われていた。
だが、プレトが作った溶液は、その辺でただで手に入るようなものばかりで作られている。だから、ラピス溶液と成分が同じなんてことは絶対にあり得ないはずだった。プレトは自分の目が信じられず、何度も何度も確認してみたのだが、やはり何度見ても、2つの溶液はまったく同じ成分でできていた。
疑問に思っているタイミングで、作業室に所長が入ってきた。他に誰もいなかったので、所長と2人きりになった形だ。プレトは思いきって話しかける。
「所長、ご覧ください。私が自作した溶液とラピス溶液の成分が全く同じなのですが、こんなことってあり得るのでしょうか」
所長はプレトの質問を聞いて一瞬、固まったように見えた。 プレトは重ねて質問した。
「ラピス溶液って、宝石が原料だったはずです。しかし私は、この溶液を宝石から作ったわけではありません」
所長の顔色が明らかに悪くなっていくのが分かった。彼はしばらく黙っていたが、やがてイライラしたように言った。
「そんなこと、あるわけがないだろう。君が見間違えたんだ」そう言って作業室を出て行こうとした。
プレトは慌てて引き留めた。
「所長も確認してください。何度見ても成分は同じなのです」
所長は面倒くさそうに言った。
「見比べたのがラピス溶液ではなかったんだろう」
「いいえ。間違いなくラピス溶液です。この瓶のラベルをご覧ください」
「ではラベルが間違っているんだろう」
所長のこめかみに青筋が浮いていた。しかしプレトは言った。
「瓶のラベルの最終確認は、所長ご自身が行っていらっしゃいますよね」
その瞬間、プレトは言ってはいけないことを言ってしまったと思った。 所長は憤慨したように言った。
「もういい、そんなことを考える暇があるなら他のことをしろ。くだらない話に付き合ってはいられない」
そう声を荒げると、今度こそ作業室から出ていってしまった。
きっとこれだ。これが原因だ。
プレトは、全くの偶然で、知ってはいけないことを知ってしまったのだ。
ラピス溶液は大きな製薬会社が専門で作っている。プレトの職場であるこの研究所は、製薬会社ととても関係が深い。そして、どちらも資源省(総合資源管理省庁)の管轄だ。
風の噂だが、所長のお嬢さんが法務省のお偉いさんのご子息に嫁いだという話も聞いたことがある。命令書に所長と法務省が連名になっていたのも、それに関係があるのかも知れない。
もしかしたら、パラライトアルミニウムの枯渇問題にかこつけて、ラピス溶液の秘密に気付いたプレトをこの研究室から追い出そうとしているのではないだろうか。レインキャニオンに行ったきり、帰って来なければいいとすら考えているのかも知れない。それに、研究所の職員が虹の採取に行ったら、政府がきちんと枯渇問題に対応しているということを世間にアピールすることもできる。
だが、これらはあくまで推測の域を出るものではない。プレトには分からないことだらけだ。
前方からチユリさんが歩いてきた。
「プレトさん、お疲れさま。どうだった?」
プレトは彼女の顔を見なかった。見たら泣いてしまいそうだったからだ。
「やはり行くことになりました」
蚊の鳴くような声で答える。チユリさんがショックを受けているのが気配で伝わってきた。
(第4話につづく)

コメントを書く