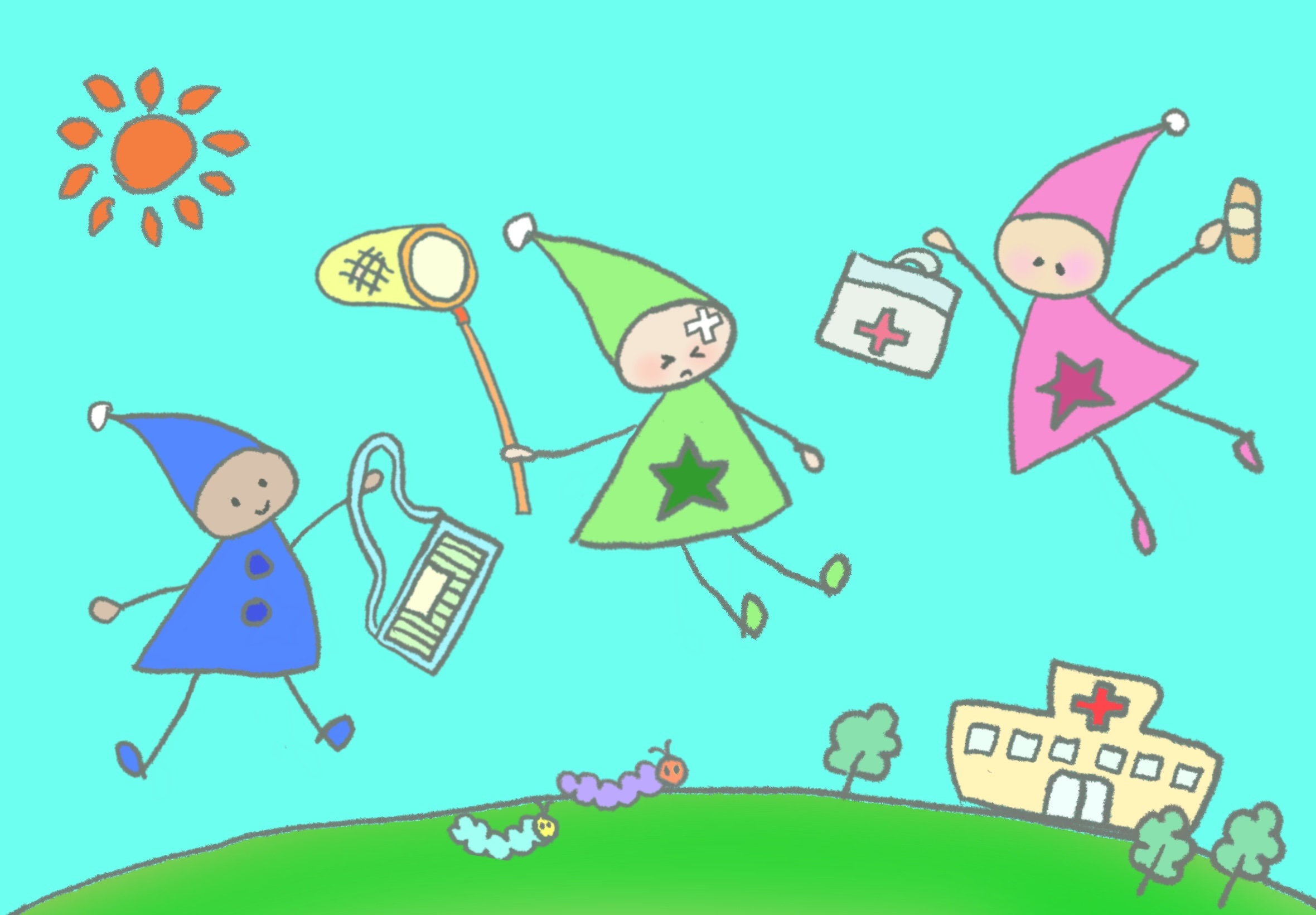
プレトはキリンパンを睨みつけたまま言った。
「まさか二日酔い? 叫んだり、ヘラヘラしたり……脳みそ故障してるの?」
男に悪態をつきながら、さっき通信機の前で、ルリスの名前を呼んだことを反省していた。ルリスの名前を彼に知られてはいけない。あくまでルリスは、ソバカスだ。彼はずっと絶叫していたから、聞こえてはいないはずだが、気をつけなければ。
「寝癖も直せないやつに言われたくねえな」
「なにその言いかた!」ルリスがキリンパンに言い返しながら、プレトの後頭部をさすってくれる。
「悪かったな。利子つけて返すからさ」彼はポケットから両手を出してブラブラさせている。悪かったとは一ミリも思っていないようだ。
ビリビリとした痛みがどんどん強くなっている気がした。毛虫に刺されると、こんなに痛むものなのだろうか。痛みを和らげたくて身体を揺らしてみたが、特に効果はなかった。ルリスが患部を見て、呻くような声を出す。
「どんどん赤い範囲が広がってるよ……」
ルリスに首の後ろを見せるために、顔を下に向けていたが、例の毛虫が視界の中を歩いているので、とても不愉快だった。しかし、刺されたのがルリスでなくてよかった。
「もう、次の街に行こうよ。病院にも行かなきゃ」ルリスがプレトの顔を覗き込みながら言う。
「……とりあえず、装備の救急セットで手当てできないかな?」
「クリームちゃんの縫合もできたくらいだし、なんとかなるかもね。手当ての方法、調べてみるよ。えーと……」
ルリスは、携帯電話でしばらく検索してから言った。
「分かったよ。患部の毛虫の毛をガムテープで取って、石けんと流水で洗うんだって」
「え、そんなことするんだ」
「必要なもの、持ってくるね!」ルリスはそう言って、ピンクのレグルスに向かう。
患部は相変わらずビリビリしていた。本当に電気が走っているみたいだ。プレトはルリスが装備を漁っている間に、キリンパンに話しかけた。
「ポケットに何か入れてる?」
「ポケット?」
先ほどルリスに患部を見てもらっていたとき、毛虫を見ながらも同時にキリンパンの腰の辺りをじっと窺っていたのだが、彼の右ポケットが不自然に膨らんでいるのが見えたのだ。特に理由はないが、それがなぜか気になった。
「入っているのは携帯電話じゃないよね」
「だからなんだよ」
「見せてよ」
「は? なんで」
「なんか気になるから。身代わりで刺されたんだから、教えてくれてもいいでしょ」
「はあ?」
自分でも不思議だったが、無性に気になって仕方がなかった。ラピス溶液の秘密に気付いたときも、こんなふうに不思議な勘が働いたような気がする。ラピス溶液のときはマイナスに転んでしまったが、今回はどうなるだろう。思いきって、すぐそばにあるポケットに手を突っ込んでみた。嫌味ばかり言われているのだから、これくらいいいだろうと思ったのだ。当然だが、やはり何かが入っていた。
「おい! なんだよ!」
キリンパンの動揺したような声を無視して、手を引き抜いた。プレトの手が握っていたのは、小さなガラスのビンだった。アルミ製の蓋には、錐で突き刺したような小さな穴がいくつも空いている。
「これなに?」
「……薬のビン」
「なんの薬?」
「それも言わなきゃなんねえのか? ドラッグなんかじゃねえから放っておいてくれよ」
それは確かに薬のビンだった。蓋の穴以外は、なんの変哲もない普通のビンだ。ラベルなどは何もない。このようなビンに入ったサプリメントを見たことがある。
「なんでこんなの、ポケットに入れてるの?」
「……さっき飲みきったものを捨てずに、ポケットに入れてたんだよ」
ちょうど飲みきった後、ひとまずポケットに入れてしまうのは理解できる。プレトも鼻をかんだティッシュなどを、ポケットに入れてしまうことがよくあるからだ。ごく稀にそのまま洗濯して、ルリスに呆れられることもあった。だが、蓋にこんな小さな穴がいくつも空いているビンは見たことがない。これでは密閉性が失われるではないか。
「救急セット、持ってきたよ」
「あ、ありがとう」
ルリスの方を向いた瞬間、キリンパンにビンを取り上げられてしまった。文句を言ってやりたかったが、やめることにした。首の後ろだけではなく、首全体がビリビリしてきたからだ。早急に手当てをしてほしかった。
「早速、やろう!」ルリスが張り切っている。
「こういうのは、可及的速やかに対応しねえとな」
「法律家みたいな言い回しするじゃん」
プレトが苛立たしげに言うと、キリンパンが固まった。表情が消え、伏し目がちになる。今の今までヘラヘラしていたのに、急にどうしたというのだろう。だが、痛みに耐えながら軽口に応じるのも億劫だと思い、放っておいた。
ルリスは調べたとおりに、テキパキと応急処置をしてくれた。患部をペットボトルの水で洗ったので、頭とTシャツがびしょ濡れになってしまった。昨日はリバースパンダから逃げるためにずぶ濡れになったが、今日は毛虫のせいでずぶ濡れだ。
「ソバカス、手当てありがとう」と、プレトは言った。「ストーカーから逃れられたと思ったら、まさかこんな目に遭うなんて……」
「そうだよね、まさかあんな虫がいるなんてね。レグルスで着替えたら?」
「そうする。次の街に行こうか」
徐々に頭が痛くなってきた。よろよろとルリスのレグルスに近付き、助手席に座った。立っているのが辛かった。ルリスが操縦席に乗り込み、しばらくすると、キリンパンのレグルスが発進した。それを追うように、ルリスもレグルスを動かす。
頭がガンガンした。まるで心臓の鼓動と連動しているようだった。
プレトは痛む額に手を当てながら、通信機に話しかけた。
「毛虫は窓から入ってきたの?」
「多分な」
「いつ?」
「さあ。虫って勝手に入って来ちまうじゃねえか」
「……そうだね」
目の前がチカチカしてきたので、そこでひとまず会話を終えた。
1時間ほど走ると、小さな街に辿り着いた。かなりの田舎だった。
キリンパンとは別行動で、プレトとルリスは小さな皮膚科に入った。ルリスが診察室までついてきてくれた。なんだか子供に戻ったような気分だった。
「あら、これは辛いでしょ」患部を見るなり、医者はそう言った。
「頭がガンガンします」
「そうだよね。でも、応急処置は完璧だよ」
ルリスがにっこりした。医者は改めて手当てをしながら、続けて話してきた。
「ここは田舎だし、毒虫に刺された患者さんはよく来るけど、これはなかなかひどいね。どんな虫かは分かるかな?」
手当てが終わると、昆虫図鑑を差し出された。果たして探し当てられるだろうか。蛾や毛虫のページをめくっていくと、毒々しいものを発見した。記憶にある毛虫と同じ色だった。
「これだと思います。ドクププって書いてありますね」
初めて聞く名前だった。
「え、これなの?」
医者がいぶかしげな顔をする。何かおかしなことを言っただろうか。
「はい。こんなふうに、赤と黄色で、紫の斑点があって……」
「これはどこにいたの?」
「この子とは別の、連れのレグルスの中です。窓から入ったとか言っていました」
「窓から? それは……うーん……」
医者はしばらく黙ってから、再び口を開いた。
「ドクププは、この辺にはいないんだよね。数も余り多くはないし、わざわざ探さないとお目にかかれないようなものだよ」
「え……」
プレトが知らないだけで、よくいる虫なのかと思っていた。だが、そうではないようだ。それならなぜ、キリンパンのレグルスにいたのだろう。
「これに刺されても熱は出ないんだけど、あなたは微熱があるね。疲れが溜まっているのかな? 思い当たる節はある?」
「……思い当たる節しかありません」
職場から命令書が届いてから、ずっと疲れが溜まりっぱなしだ。
「そっか。どちらにしろ、薬を塗って安静にしておくしかないわね。数日分処方しておくね。発熱もしてるから、大人しくしていたほうがいいよ」
「はい」
ルリスと一緒に病院を出て、体を引きずるように駐車場に向かっていった。元気におしゃべりしている子供たちとすれ違った。
みんな帽子を被り、虫とり網と虫かごを携えている。いかにも夏らしい光景だった。
そのとき、キリンパンが持っていた空きビンを思い出した。プレトは振り返り、改めて子供たちを見た。そして視線を、彼らの虫かごに移した。そこにはどんな虫が入っているのだろう。当然だが、虫かごにはいくつも穴が空いている。空気穴だ。では、あのビンの蓋に空いていた穴は?
嫌な予感がプレトの中で、さざ波のように広がっていった。
(第25話につづく)

コメントを書く