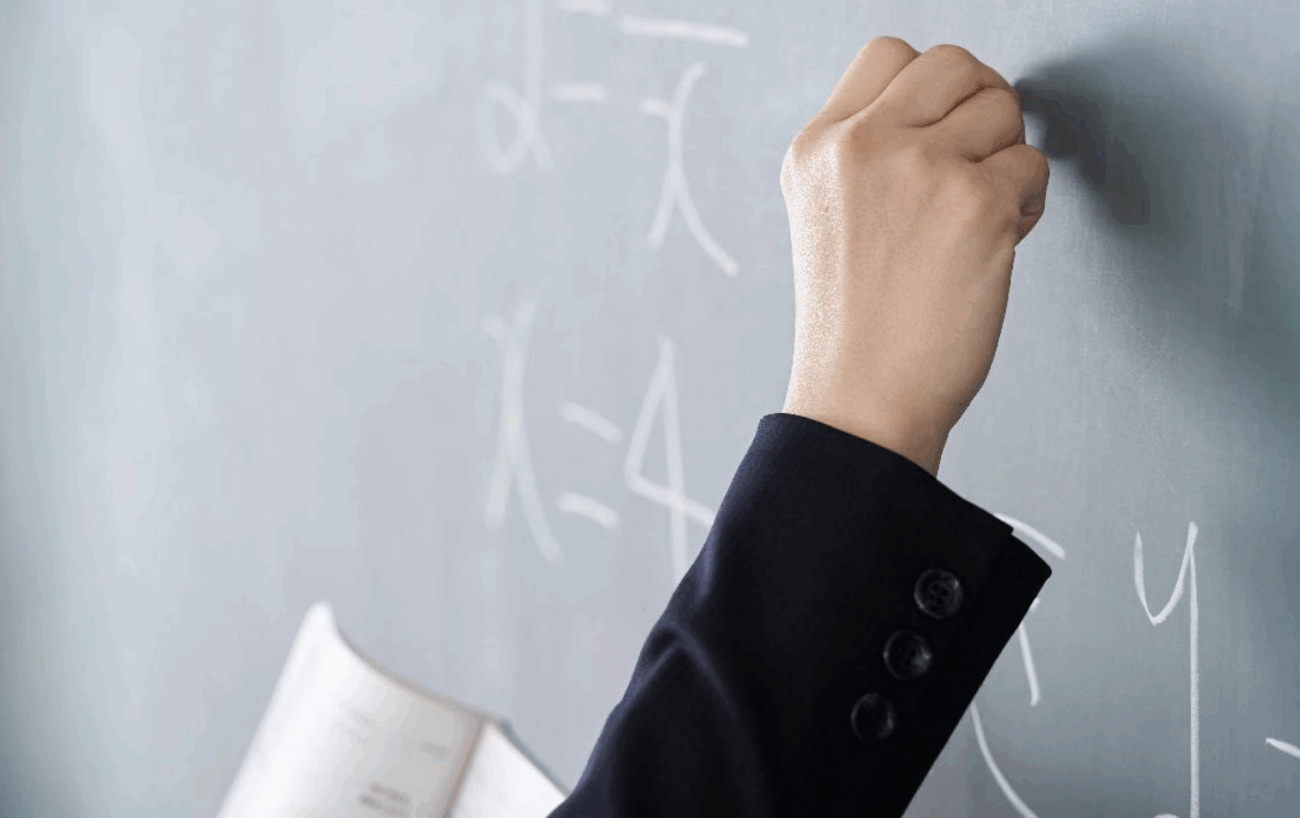
経済協力開発機構(OECD)による最新の調査で、日本の教員の業務時間が加盟国の中で最も長いことが分かりました。
日本の教員業務時間、また最長 課外活動や事務が要因 OECD調査 https://t.co/prHGkDxUuM
— 毎日新聞ニュース (@mainichijpnews) October 7, 2025
OECDは加盟国などを対象に、5〜6年ごとに「国際教員指導環境調査」を行っており、今回は16の国・地域の小学校、55の国・地域の中学校が参加しました。
日本では小学校と中学校それぞれ約200校の校長や教員が、業務時間や仕事上の課題について回答し、1週間当たりの業務時間は小学校で52.1時間、中学校で55.1時間と、2018年の前回調査に続いて最も長い結果となりました。
業務の内訳を見ると、日本の中学校では部活動など「課外活動」にかける時間が1週間当たり5.6時間と、国際平均1.7時間の3倍以上に上っています。
事務作業にかける時間は、中学校で5.2時間(国際平均3時間)、小学校は4.5時間(同2.7時間)と、こちらも国際平均に比べて長い傾向が見られます。
また、各校の校長に「質の高い指導を行う上で不足している教育資源」について尋ねたところ、「教員が足りない」と回答した割合は、小学校で40.7%と前回の19.2%から2倍以上に増えました。
中学校でも35.6%と前回より8.1ポイント増加しており、いずれも国際平均を10ポイント以上、上回る結果となりました。
この結果を受け、文部科学省は、残業時間の上限設定や部活動の地域移行などの取り組みにより、一定の改善は見られるものの、「依然として課題は多い」として、働き方改革をさらに進めていく方針を示しました。
現在、大手メディアは教員不足を強調して報じており、文部科学省も人手不足を補うため、教員免許を持たない人まで教育現場に派遣できる制度を拡充していることから、子供たちの安全や教育の質への影響が懸念されています。
全ての子供たちが安心して学べる教育環境が整備されますことを心から祈ります。
◯【崩壊する教育現場】全国の教員不足、過去最多の4714人「現場は限界を迎えている」

コメントを書く