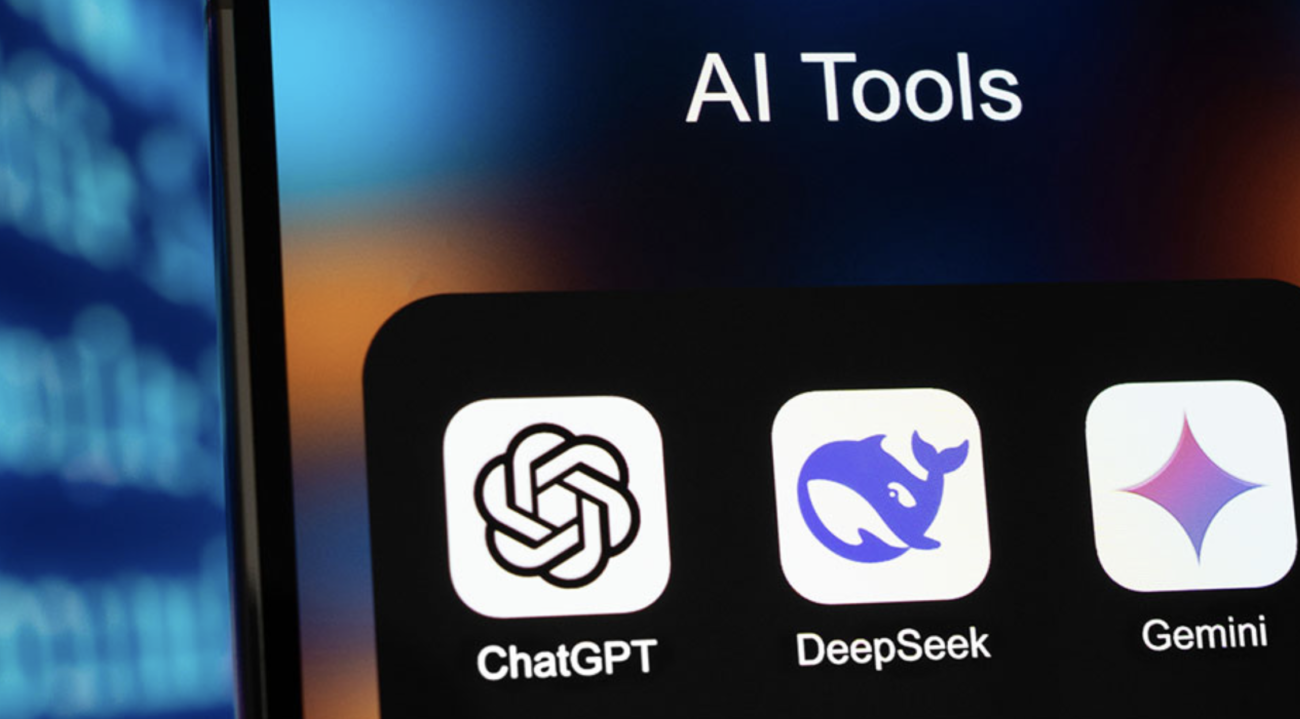
2025年に実施された東京大学の入学試験問題を生成人工知能(AI)に解かせたところ、最難関とされる「理科3類」で合格水準に達する成績を収めたことが分かりました。
【AIが東大理科3類「合格水準」】https://t.co/qdD78r1Mrf
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) April 5, 2025
AIベンチャーのライフプロンプトによると、米オープンAIの「o1(オーワン)」と、中国の新興企業「DeepSeek(ディープシーク)」が開発した「R1」に、それぞれ大学入学共通テストと東京大学の前期日程・2次試験を解かせたとのことです。
その結果、550点満点中、「o1」は文系の文科1〜3類で379点、理系の理科1〜3類で374点を記録し、いずれも合格最低点を上回りました。
また、「R1」も同様に、文系・理系ともに合格水準に達したとのことです。
2次試験の英語(120点満点)では、「o1」が93点、「R1」が92点と高得点を出しましたが、国語(120点満点)では「o1」が71点、「R1」が75点とやや低めとなり、小説の設問で得点が伸びませんでした。
数学では図形の問題で苦戦し、「o1」が80点満点中で40点、「R1」は18点にとどまりました。
一方、三角形の物体の移動に関する物理の問題では、図形の変化を正確に読み取って正しく回答するなど、高度な処理能力を発揮しました。
ただし、世界史の問題では、産業革命期の都市と人口の推移に関する設問で、誤った都市名を選ぶなど、人間ではあまりしないようなミスも見られたとのことです。
このようにAIには得意・不得意がありますが、年々その精度は向上しており、使い方次第では多くの雑務や作業を人を介さずスムーズにこなすことができるなど、さまざまな分野での活用が進んでいます。
しかし、その一方で、中国のDeepSeekが開発した「R1」については、個人情報の収集といったスパイ活動に利用されているほか、マルウェア(悪意あるプログラム)や火炎瓶の作り方など、犯罪に悪用できる情報を回答することが明らかになっており、自治体などで使用を禁止する動きが広がっています。
最先端技術が正しく用いられ、人々の生活向上につながる分野がさらに発展していきますことを心から祈ります。
◯中国の生成AI『DeepSeek』、収集データを暗号化しないままByteDance(TikTokを運営する企業)の管理サーバーに送信していることが判明
◯イーロン・マスク、孫正義らのAI投資計画を疑問視 「ソフトバンクが確保している資金は100億ドルをはるかに下回る。確かな筋から聞いた話だ」とXに投稿
◯『チャットGPT』の開発元・オープンAI、世論操作にAIが悪用されていると発表 ロシア、中国、イラン、イスラエルを拠点とする5つのグループを特定

コメントを書く