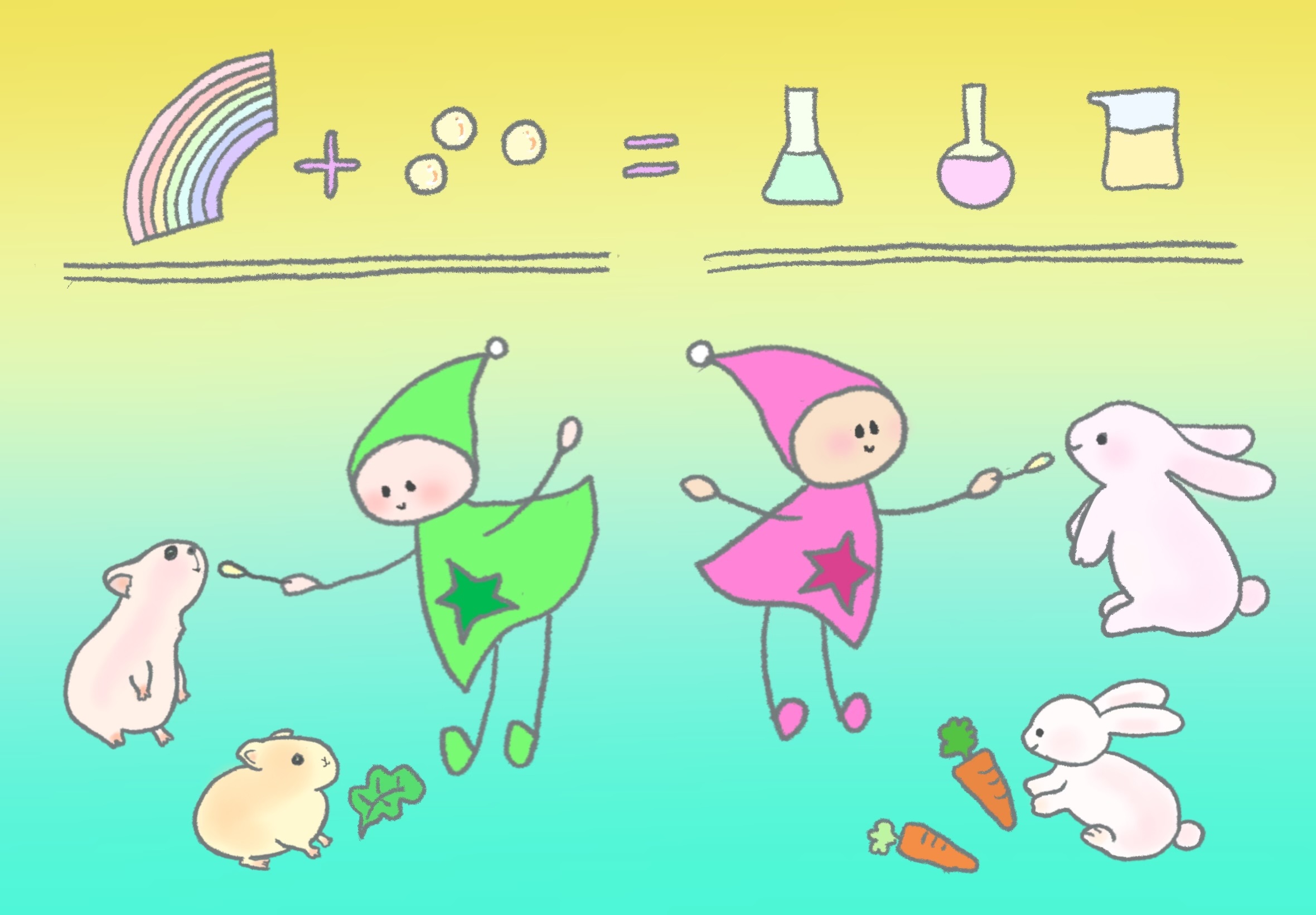
「所長め……」
ルリスが恨み言を呟きはじめた。
「プレトをパラライトアルミニウムに沈めようだなんて、絶対に許さない。取り巻き連中も……肥溜めに落とした後、土下座させてやる」
「もしもあのまま溺死していたら、私の出汁入りパラライトアルミニウムが市場に流通していたのかな」
「怖いこと言わないで! もう、絶対に所長をぶっ飛ばす! 絶対にダメージを与えてやる!」
ルリスはそう決意を口にすると、さらにこう言った。
「それより、プレトはこのまま死んだフリをするのはどう? 研究所も欠勤して、外部と連絡を絶つの。そうすれば、今までみたいに狙われることもないでしょ?」
「……確かに。奴らには死んだと思わせていた方が色々と得策かも。でも、二人とも無職ってヤバいんじゃない? しばらくは貯金でやっていけるだろうけど」
「ムーン液が解毒剤としてたくさん売れたら、なんとかなりそうじゃない?」
「確かにそうだね。もし何もかもうまくいかなかったら、レインキャニオンで隠居しよう。肉塊を捕まえて、珍獣として売るか」
「スリルがあって面白そう」
ルリスが操縦しながら吹き出した。つい先ほどまで溺れかけていたとは思えないぐらい、車内が和やかな雰囲気に包まれていった。
翌日、プレトは計画通りに無断欠勤した。研究所から何度も電話がかかってきたが、全て無視した。おそらく、何も知らない事務所の職員がかけてきたのだろう。
「じゃあ、早速だけど、ムーン液が安全かどうか、生き物たちで治験するよ。不安だと思うから、ルリスは見なくていい」
「大丈夫、一緒にこの子たちを見守る。何かあったらすぐに動物病院へ連れて行けるように、支度をしておくね」
プレトは生き物たちにムーン液を少量だけ舐めさせた。少し時間を置いて観察してみたが、特に変化は見られなかった。ゴルゴンゾーラと名付けられたモルモットが突然、仰向けになったときは焦ったが、ただ寝ているだけだと分かって安心した。哺乳類ではないスカイフィッシュも元気に飛び回っている。
「みんな平気そうだね。よし、私も」
指先に付けたムーン液をペロッと舐めた。
「わあああ! やめてよ! 吐き出して!」
目を見開いたルリスに身体を揺すぶられる。
「大丈夫だよ」
「なんでそんなこと言えるの! 絶対に死なないで!」
「死なないよ。私さ、レインキャニオンで虹の赤い部分を食べたし、昨日はパラライトアルミニウムを飲んじゃったんだ。だけど、なんともないんだよね。カスタードルフィンの真珠にも毒はないから、ムーン液も安全だという確信がある。それに、これからワクチン被害者に治験のお願いをするとき、私も舐めましたって言った方が安心して協力してもらえるでしょ?」
「そういうものなの?」
「単純に舐めてみたかったというのもある。無味無臭だね」
「研究者の好奇心、怖い」
結局、プレトの身体にも変化は起こらなかった。治験の合間、〈アネモネ〉が譲ってくれた真珠をハロに押しつけてみたが、これもまたぷくぷくと発泡し、ムーン液に変化していった。それを見たルリスが驚きの声を上げた。
「虹の時と、量が全然違う! ハロのほうが断然多いね」
「倍以上はあるよね。もしかして、虹よりハロのほうが密度が濃いのかな? こんなに小さな破片から、これだけ大量のムーン液ができるなら……国民全員に配るのも夢じゃない!」
「絶対にできるよ! この後は、スパイク肺炎ワクチンの被害者に治験してもらうの?」
「そうだね。体調を崩した人たちがもう入院しているかもしれないから、研究所の付属病院にコンタクトを取りたいな」
「でも、行方不明中のプレトが連絡したらまずいんじゃ……」
「私もそう思う。だから、チユリさんに協力してもらおうかなと。研究所内で信頼できるのは彼女しかいないし、一人で倉庫番をしているから、こちらの情報がうっかり漏れる可能性も少ないと思うんだ。最近まで採取チームの管理職だったから、病院の方にも人脈があるかもしれない」
終業時間を待ってチユリさんに電話してみると、心配そうな声が聞こえてきた。
「二人とも元気なの? プレトさんが無断欠勤したって噂を聞いたから気になっていたのよ。何かあったの?」
「実は……」
プレトは昨日起きた恐ろしい出来事を話し、身を守るために行方不明のフリをすると伝えた。携帯電話越しに息を飲んだ気配が伝わってきた。
「まさか、そんなことが……」
「なので、地下室の存在は知らない体で過ごした方がいいと思います。チユリさんには同じ目に遭ってほしくないので」
「分かったわ。教えてくれてありがとう。ぜんぶ、内緒にしておくわね」
「ありがとうございます。で、本題なのですが、ワクチンの解毒剤になりそうな液体ができあがったので、ワクチン被害者に治験の協力をしてもらいたいと考えているんです。動物での治験は済んでいて、私も舐めましたが、この通り、元気です」
「本当に解毒剤ができたの? すごいわね!」
「なので、もしツテとかがあったら、スパイク肺炎に罹った人を紹介していただけないかなと……」
「うーん。私にはそういう権限はないけど、付属の病院に知人がいるから、内情がどんな感じか訊くことはできるかも。それでもいいかしら」
「ぜひお願いします!」
「じゃあ、また連絡するわね」
通話が終わると、ルリスが期待に満ち溢れたような表情になった。
「ワクチンの解毒剤ができたって言ったらさ、病院の方から治験を申し出てくる展開にならないかな! それで、協力してくれた人たちがみんな元気になって、あっという間にムーン液が世界中に普及するの!」
夢のような話だが、それが実現したらワクチンを食べた全員が助かるだろう。プレトも期待してチユリさんからの連絡を待った。
数十分後、チユリさんから電話がかかってきた。意気揚々と電話に出たものの、沈んだ声が聞こえてきた。
「知人に電話をしてみたんだけど、ワクチンに関することは外部に話してはいけないって、病院から指示されているみたい……」
「指示ですか?」
「うん。指示というより、命令って感じかしら。国から『ワクチン被害に関する情報は外に出すな』って警告されている上に、補助金が出ているらしいの」
「お金で口止めしているということですか!」
「そうみたい。でも、知人もプレトさんたちのフォロワーみたい。ワクチンについて、こっそり教えてくれたわ。アレは特別なプロセスで承認されたんだって」
「特別なプロセス……?」
「ワクチンの効果を『推定』で判断して承認したようなの。パンデミック宣言の陰で、スパイク肺炎ワクチンを普及させるために、新しい承認プロセスを作っていたらしいわ」
「推定ということは、効果の確証も実績もないのに、承認されたということですか?」
「そうらしいわ。国にとって『スパイク肺炎ワクチンは特別』ってことね。だから、有効な解毒剤ができたとしても、薬としての申請は通らないかも知れない。治験の許可すら下りないかも……」
チユリさんの声色は暗い。治験ができない? 申請が通らない? それじゃあ、ムーン液を流通させることはできないのか?
「役に立てなくてごめんなさい……」
蚊の鳴くような声が聞こえた。
「いえ。病院の内情を知ることができて、とても助かりました」
「私にできそうなことがあれば言ってちょうだいね。うまくいくように、お祈りするわね」
通話が終わると、ルリスが肩を落とし、ぶつぶつと呟きはじめる。
「所長め……悪い奴らめ……」
正直、プレトも気力が萎えていくのを感じた。せっかくムーン液ができたのに、どうしたらいいと言うのだ。
(第70話につづく)

コメントを書く