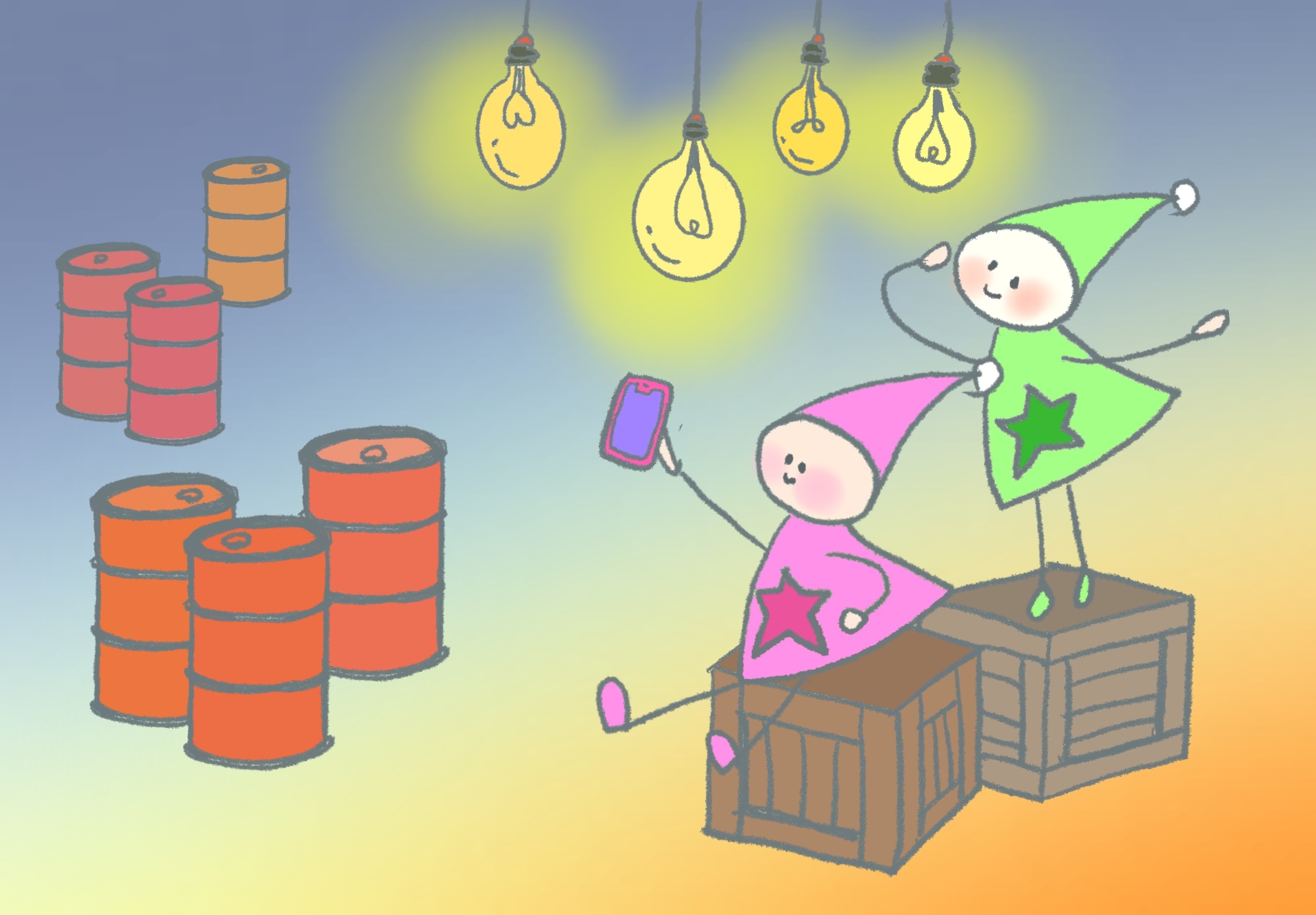
助手席に座ったプレトが、クライノートを簡単にチェックすると、ピリピリしている投稿で溢れかえっていた。政治家の悪口でいっぱいだった。パラライトアルミニウムの高騰で、生活必需品が倍の値段になるのだから、当然といえば当然だろう。
SNSのアカウントを作り、共有した後、2人はすぐに出発した。誰かが様子を見に来る可能性もある。せっかく奇跡的に脱出できたのに、うっかり捕まっては元も子もない。鉢合わせを避けるためにも、先に進むことにしたのだ。
「クライノートでは、パラライトアルミニウムの枯渇問題が話題になってるみたい。文章からイライラが伝わってくるよ」
プレトがそう話しかけると、ルリスは答えた。
「やっぱりね。ずっとだんまりしていたくせに、突然、値上がりすることになったから、みんなも怒ってるんだよ。話題になっているワードを投稿文に入れると、見てもらえる確率が上がるよ」
ルリスがムスッとして言った。政府や研究所の、枯渇問題への対応がずさんで、気に入らないのだろう。
「そういうシステムなのか。それじゃあ、パラライトアルミニウム関連のワードが含まれるように、文章を作ればいいかな」
プレトたちはちょうど、パラライトアルミニウムの原料となる虹を採取しに向かっているところだ。もしかすると、投稿内容に注目してくれる人が出てくるかもしれない。しばらく機能をいじくりまわしていたが、クライノートは操作はとても簡単で、すぐに使い慣れてきた。投稿文には文字数の制限が設けられていたが、特に困ることもなさそうだ。写真や画像、動画も投稿できる。
ルリスは出発してからこれまで、様々な場所で写真を撮っていたらしく、出発前に一通り送ってくれた。いつの間にこんなものを撮っていたのだろう。プレトが携帯食料を口に運んでいる写真まである。半目になっていて、とてもマヌケな顔をしていた。プレトは、今まで起きたトラブルを綴った文章に、関係ある写真を添えて投稿していった。
「こういうのって、どのくらいで反応がもらえるものなの?」と、プレト。
「できたてほやほやのアカウントだからね……最初は誰にも見られないと思うよ。みんな自分が興味がある話題に注目するから、私たちの投稿のどれかが誰かの興味に引っかかれば、見てもらえるかも」
「運が良ければ、見てもらえるってことか」
運が良ければ……か……
自分で言った言葉だったが、これまでの運が悪すぎて、そう簡単にうまくいくとは思えなかった。誰か一人でも、あいつらの悪事を知ってくれたらな……
そのとき、携帯電話に通知が入った。確認してみると、なんと誰かにフォローされたらしい。どうやら、クリームを保護したという投稿に反応してくれたようだった。〈アネモネ〉というアカウントで、投稿内容などを見ると、カスタードルフィンへの興味が強いらしい。
……なるほど、こうやって知らない人と繋がることができるのか。
「さっそくフォローしてくれた人がいるぞ。クリームのかわいい写真のおかげかもしれない」
「やったね! その人が一番乗りだね」
「こんな予想外のルートで見てもらえることもあるんだ。このままぼちぼち続けていけばいいかな」
窓の外を見ると、周りの木々が大きくなびいていた。レグルスの中にいると分からないが、風がかなり強いようだ。たくさんの雲が、競争するように前から後ろへと猛スピードで流れていく。今は頭痛が弱くなってきた。景色を楽しむ余裕があるのはいいことだと、つくづく思った。
ふと前方に目を向けると、道路がいつの間にか砂利道になっている。そのまましばらく進んでいくと、中途半端に切り拓かれた森に辿り着いた。街に着くはずだったのに、人影もレグルスも見当たらない。
「あれ? 道、間違えちゃったかも……」
ルリスがレグルスのスピードを落としながら呟いた。
「工業地帯に着くはずだったよね? 目印もなかったから、どこかで逸れちゃったかな」
様子を伺いながらそろそろと進むと、広場のような空間に出た。切り株を掘り起こしたばかりのようで、所々、土の色が変わっている。プレハブや仮設トイレがいくつか設置されていて、工事現場のような、資材置場のような雰囲気だった。
「なんというか……『とりあえず置いた感』があるね」プレトは感想を言った。
「うん。つい最近、作業に取り掛かり始めたような感じがするね。森も開拓したばっかりというか、開拓している途中に見える」
「工業地帯が近いから、ここにも工場を建てるのかな?」
「そうかもね……あれ……?」
ルリスが口を半開きにして立ち止まった。ルリスの視線の先をたどってみると、簡素な物置小屋のような建物があった。鍵をかけ忘れたのか、扉が風に煽られ、バタバタと開いたり閉じたりしている。その扉の隙間から、中がわずかに見えた。
驚いたことに、そこには密林で痛い目に遭わされた、あの円錐型の機械がずらりと並べられていた。プレトは思わず息をのんだ。どうしてあれがこんなところに? ここは、あれを保管する場所なのだろうか。
隣にいたルリスが、眉をひそめながら言った。
「昨日の今日で、またあいつを見るなんて……」
「えーと、どうしようか……」
少し間を置いてから、ルリスが答えた。
「覗いてみよう」
周りに人けがないことを確認し、2人でレグルスから降りた。物置小屋の周りを一周してみたが、防犯カメラのようなものは見当たらない。設置前なのかもしれない。中に入ろうとしているルリスに声をかけた。
「ほんとに入るの?」思わず小声になった。
「なにか収穫があるかもしれないからね。所長たちの悪事を暴くヒントになりそうなものは、積極的に集めておかなきゃ」
力強い言葉だったが、ルリスも小声になっていた。プレトと同じで、内心は不安でいっぱいなのかもしれない。
「一緒に入ろう」
プレトは、ルリスに身を寄せて言った。同時に足を踏み入れると、中は思ったよりも広かった。なんというか、新しいにおいがする。置かれたばかりの小屋なのかもしれない。窓がないので、とても薄暗い。入り口付近にあるスイッチを押してみると、照明がついた。天井からぶら下がっている電球が、一斉に点灯したのだ。
見ると、プレトたちから見て左の壁に沿うように、円錐型の機械がいくつも並べられていた。右の壁側には、ドラム缶や一斗缶が置かれている。2人は左の、機械の方に近付いていった。
円錐型のそれには、手のひらサイズの、ロゴマークのようなものが描かれていた。本体の色とほとんど同化していて、近くで見なければよく分からない。どうやら、文字か数字を崩したデザインのようだ。
「これを造った会社のロゴマークかな?」と、ルリス。
「そうかもね……」
置かれている機械は、形も色も全て同じものだったが、大きさはいくつか種類があるようだった。プレトたちが嵌められたものより、大きいものもあるし、小さいものもある。ふと、面妖な光景がプレトの脳裏に浮かんだ。
……世界の果てには、この機械のようなテトラポットが並べられていて……必要以上の海水が、大地に侵入してくることを防いでいるような……そんな気がした……そんなわけ、ないだろうけど……
ルリスに背中をつつかれ、我に返った。今度は小屋の右側、ドラム缶に近付いていった。そのそばには、一斗缶も積まれている。プレトはそれらを見て、目が点になった。全てに『パラライトアルミニウム』と書かれていたのだ。
「これが全部パラライトアルミニウム? なんでこんなところにあるんだ……それにこんな量、見たことない」プレトはひとり言のように言った。「こんなにあるのなら、値上げする必要なんてないじゃん。なんで枯渇しそうなんて言うんだろう」
「……」ルリスも呆然としている。
「研究のときも、レグルスにも、ほんの少しずつしか使わないのに……」
プレトはそう言いながら、昨日見たものを思い出した。落雷によって壊れた円錐型の機械から、液体が流れ出ていた。
「この機械の燃料って、パラライトアルミニウムなんじゃ……だから同じ小屋に置いてあるのかな……」
悲しい予想が、プレトの口からこぼれた。もしあの液体がパラライトアルミニウムだったとしたら……この機械は、レグルスとは比較にならないほど、大量に消費しながら動いていることになる。小屋全体が風に打たれて、カタカタと細かく震えていた。プレトの手も震えた。体調のせいだけではない。見てはいけないものを……しかし、知るべきことを突然目の前に突きつけられた気がした。
「枯渇問題って」と、ルリスが口を開いた。「消費量が増えたせいって言ってたっけ……こんな罠みたいな機械、日常で使うわけないのに、誰がなんのために作っているのかな……」
「……分からない」
「パラライトアルミニウムって、もしかしたら……レグルスとこの機械以外にも、使い道があったりして。こんな簡単な造りの小屋に、無造作に置いておくくらいだから、本当はまだ沢山あるのかなって……それが枯渇しそうなぐらい、もっと大量に消費する理由が他にもあるのかも知れない」
「……」
「あ、思いついたことを適当に喋っただけだから! ぜんぜん違うかもしれないから! わたしも喋りながら混乱してるし!」
プレトはため息をついた。問題と疑問が脚に絡み付いているように思えた。うっかり道を間違えた結果、こんなものを見付けることになってしまった。
一体この地域で……いや、この国では何が起きているのだろう。国民の知らないところで、黒くて禍々しいものが渦巻いているような気がした。
(第36話につづく)

コメントを書く