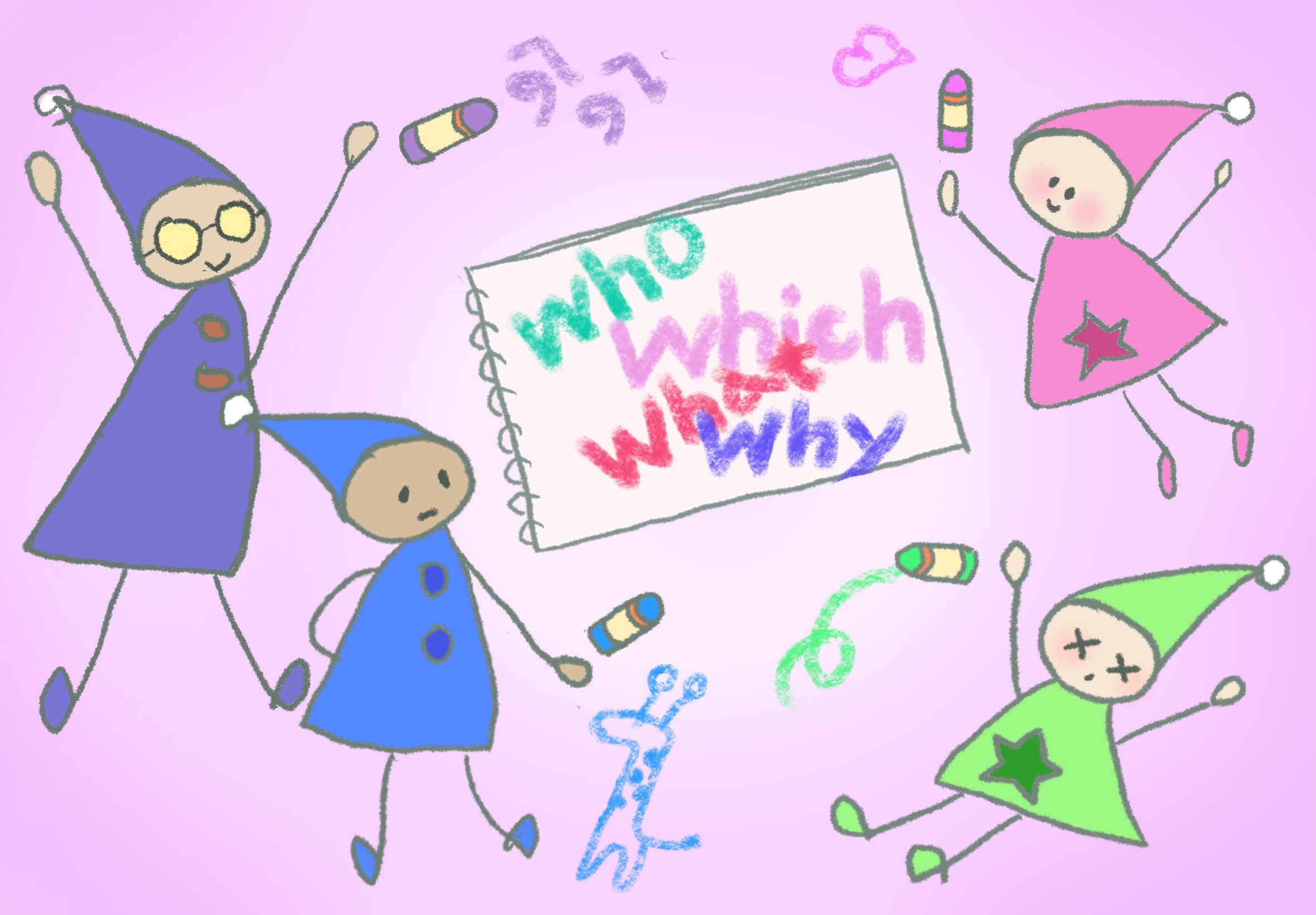
タンザロアニシン……そうだ、思い出した。
子供の頃に読んだ、マンガのキャラクターに名前が似ているのだ。
そんなことを……思い出したところでね……
草が柔らかく踏まれる音がした。スニーカーを履いた友が近づいてくる。ルリスがテントの開口部のそばにしゃがみこみ、プレトの襟足の髪を持ち上げると、一瞬息をのんだのが分かった。
「うそでしょ! 悪化してる! どうしよう、街までかなりあるのに!」
「さっき部長補佐が、電話で……病院に行っても、仕方ないって……遅効性の毒で……助かったって、聞いたこと、ないって……」
ルリスの呼吸が浅くなり、明るい茶色の瞳が左右に揺れる。プレトの右手を両手で握り、ゆっくりと口を開いた。
「なんで……どうして……」ルリスの声が震えている。
首が全体的に痛く、同時に痒くなってきた。プレトは思わず「ごめん」と蚊の泣くような声で言った。
「なにか分からないの?」ルリスの声色が切実だった。
「……毒の名前が、タンザロアニシンって、ことしか……」
「そんなの、初めて聞いたよ……」
ルリスがそう言って、眉根を寄せる。苦しそうな表情だ。
「……手当てしておくね」そう言って、処方された薬を首に塗ってくれた。
「ありがと……」そう声をかけるなり、額から滝のような汗が出てきた。
どこかの内臓が、ねじれるような痛みを放っている。プレトは呻きながら身体を丸めた。視界の端で、ルリスが震える両手を口元に当てているのが見えた。瞳が恐怖の色に染まっている。せっかく、きれいな琥珀色なのに。
そのとき、キリンパンが彼のレグルスから降りてきた。その音を聞いたのか、ルリスが彼のもとに走っていき、突然、男の肩や胸の辺りを拳で殴りはじめた。ルリスが何かを叫んでいる。泣いているようだ。きっと、プレトがこうなったことを責めているのだろう。プレトは眼の前がチカチカして、胃液がせりあがってくるのを感じた。頭蓋骨が割れるように痛い。一体どうしたらいいのだ。顔が勝手に歪む。
「プレトちゃん、大丈夫? ソバカスちゃんはどうしちゃったの?」声が降ってきた。フーイだ。
「私……死ぬかも」プレトはボソリと呟いた。
「んんんー?!」
「毛虫の、毒の、せいで……」
「……」
彼の顔は逆光で見えなかった。彼は無言で立ち去り、プレトは目を閉じた。
しばらくすると、「お見舞いだよ、こっそり持ってきちゃった」と、フーイの声が聞こえた。ゆっくりと目を開けると、頭の近くに何かが置かれているのが分かった。
これは? カードと……ビン?
ビンの蓋はアルミ製に見える。いくつか穴も空いている。これはもしかして、キリンパンが持っていたものだろうか。未だにルリスの怒った声が聞こえてくる。
「ソバカスちゃんが白状しろって怒ってるよ。その間に、キリンパンちゃんのレグルス、漁っちゃったー」フーイが教えてくれた。
彼はプレトに背中を見せながら地べたに座った。プレトは、霞んできた目を凝らしてビンを見た。アルミでできた蓋の穴の淵は、外から内に向かって、かすかにそり返っている。蓋の上部から、針やキリなどの細くて尖ったものを刺したようだ。
ゼリーベンゼン加工の錠剤が入ったビンも、穴が空いた蓋で閉じられている。が、携帯電話で調べた限りでは、もっときれいに処理されていて、穴自体も規則的に並んでいた。プレトの目の前にあるものは、ドクププが窒息しないように空けられた、空気穴のようにしか見えなかった。
震える手をカードに伸ばすと、社員証ということが分かった。しかも製薬会社の社員証だ。ラピス溶液を専門で作り、利益を上げている、あの大きな製薬会社だ。キリンパンの顔写真が載っている。氏名欄には『パンデア』と書かれていた。キリンパンのパンは、本名から取ったのだろうか。
プレトはふと思い立ち、携帯電話で社員証とビンの写真を撮っておいた。証拠写真を残そうと思ったのだ。しかし、手の震えが止まらず、ブレてしまったかもしれない。フーイがこちらに背中を向けたまま、話しはじめた。
「おれも、なんか怪しいと思ってたんだよね、パンデアちゃんのこと」
全員にちゃん付けなんだな。一応、こちらの肩を持ってくれているのだろうか。だが、フーイのことも名前しか知らない。それに、彼の言葉はどことなくセリフっぽさがある。なんとなく……なんとなくだが、この男のことも、完全には信用しない方がいい気がした。
……全身の細胞が金属になったかのように重く感じられた。胃酸が喉まで焼きはじめている。突然、フーイが座ったまま、ルリスとキリンパンをこちらに呼び寄せた。彼の声が頭の中で響き、ぐわんぐわんする。脳が釣り鐘になってしまったみたいだ。
ルリスが先にやってきて、フーイが例のビンと社員証を手渡した。ルリスはそれらを見ると、目を丸くして言った。
「プレトが言ってた怪しいビンって、もしかしてこれのこと? あの人、パンデアっていうんだ……」
プレトはゆっくりと頷いた。ルリスの声が、こちらに歩いてきたキリンパン……いや、パンデアの耳にも届いたらしい。彼はルリスの手からビンとカードをひったくり、信じられないというような表情でフーイを見た。ルリスがパンデアに向かって、激しく捲し立てた。
「やっぱりあなたがやったんでしょ! プレトがレグルスを覗いてる間に、首に毛虫を落としたんでしょ! わざわざ用意してたんでしょ! 最初からこうするつもりだったんでしょ!」
「……」
「ビンは捨てたって言ってなかった?!」
「捨てたつもりになってたんだ」
「うるさい! 早く認めなさいよ!」ルリスの怒鳴り声が震えている。
パンデアは、大きくため息をついてから、ゆっくりと口を開いた。
「ストーカーを追い払ったのは、オレだぞ。助けて殺すって、そんなことするか?」
ルリスは口を開けたが、そこからは何も言葉が出てこなかった。そうだ、わざわざストーカーを追い払った上で、毒虫で殺そうとするなんて、そんなことがあるのだろうか。その大きな矛盾に、ずっと引っかかっていた。
「でも、弱いくせにお酒飲んだり、突然、家に帰れとか言ったり、本当の名前も言わないし、変だよ!」ルリスが振り絞るように声を出した。
「そんなに変か? 人間なんてそんなもんだろ。それに、オレはおまえの名前、知らねえよ」
ルリスの言葉が再び途切れた。そう言われてしまうと、何もかも『性格』という一言で、説明できてしまう気がした。
「パンデアちゃん、製薬会社の人だったんだねー」とフーイ。
パンデアが、フーイに向かって顔をしかめた。憎しみの感情がこちらにも伝わってくる。プレトは、自分の着たTシャツが汗でじっとりと濡れていることに気がついた。今日は涼しいから、気温のせいではないはずだ。きっと身体が全力で、体内の毒を絞り出そうとしているのだろう。タンザロアニシンはジワジワ効く毒だと部長補佐が言っていたが、あとどれくらいもつのだろうか。
プレトには、世界が、クレヨンでグチャグチャに落書きされた画用紙に思えてきた。一つ一つの色はきれいでも、乱雑に乗せると汚くなってしまう。
分かることが増えるほど、分からないことが増えていく。頭が回らなくなってきた。
どうしてこんなことになってしまったのだろう。
ただ……ただ、虹を採取したいだけなのに。
ただそれだけなのに……
(第29話につづく)

コメントを書く