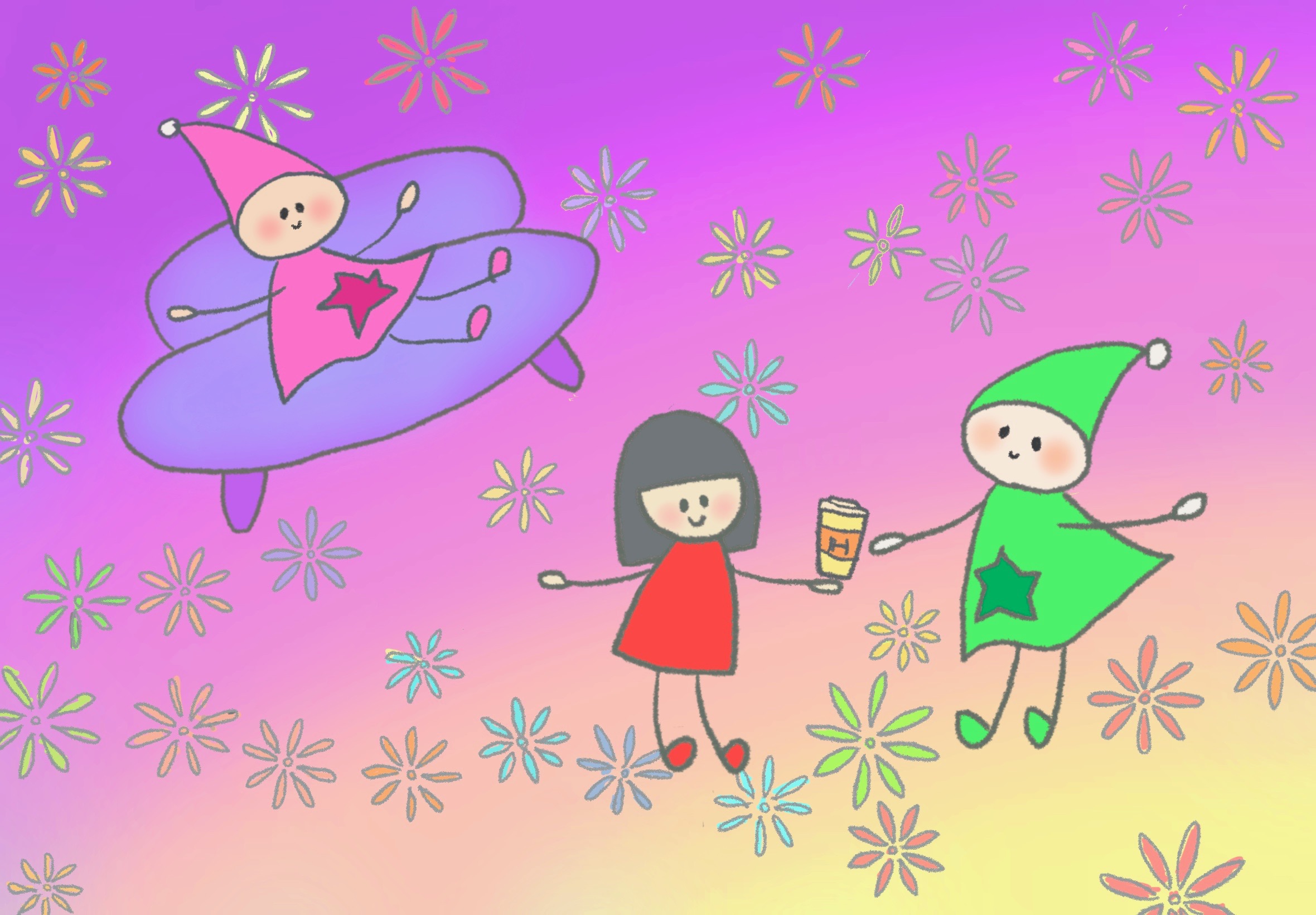
不規則になりかけた心臓を叩き、プレトは口を開いた。
「同期と話せますか? 直接話したら、何か分かるかもしれないので⋯⋯」
「分かった。探してくるわね。こっちからまた連絡するわ」
一旦、通話を終え、ルリスに声をかけた。
「チユリさんが同期を見付けたら、直接話してみる」
ルリスは居心地悪そうに話しはじめた。
「わたしさ、怒ってないからね。治るって言われたし、薬が効いてて今はあんまり痛くないし、平気だから」
「優しいね」
いつも通りに発声したつもりだったが、言葉の端にトゲがあることに自分でも気がついた。ルリスが傷付けられるなんて、どうしても受け入れられない。
「怒ってるの?」ルリスに問われた。
「もちろんだよ、同期に対してね」
「どのくらい?」
「キレすぎて声変わりしそうなくらい。私がキリンパンのせいでドクププに刺されたとき、ルリスはこんな気持ちだったのかな」
「⋯⋯きっとね」
ルリスがそばに来て肩を抱いてくれた。けが人に励まされてしまった。気を取り直し、ルリスに質問した。
「着替えとか手伝おうか? 歯磨きとかしてあげよっか? 両手が不自由だと大変だよね?」
「いやいや、大丈夫だから! 大抵のことはできるから」
「ほんとに? やせ我慢しなくていいんだよ」
「してないよっ。助けてほしいときはちゃんと言うから」
「はいはい、分かったよ」
ルリスがおかしそうに笑っている。その顔を見て、少し気持ちが落ち着いた。
すると、チユリさんから連絡が入った。同期を見つけたから、ビデオ通話をしようとのことだった。一人で寝室へ移動し、ビデオ通話を始めた。画面の向こうには、同期とチユリさんが並んで座っている。チユリさんは悲しそうに、同期は所在なさげに見えた。最初に口を開いたのはチユリさんだった。
「救護室で見付けたのよ。この人もケガしたみたい。ウチワモルフォの鱗粉を素手で扱ったせいだと思うけど」「君がやったの?」
プレトは同期に質問した。
「⋯⋯」
答えはなかった。プレトは続けて質問した。
「鱗粉はどこで手に入れたの?」
「⋯⋯」
「ねえ、なんでこんなことしたの。ルリスがケガしちゃったよ」
「⋯⋯」
「ただのイタズラでこんなことするとは思えないし、君の独断とも思えないし、誰かに指示されたんでしょ」
同期は何も言わなかったが、目が泳いだのが分かった。きっと図星なのだろう。
「こんな危険なことさせるなんて、指示した側は君のこと、大事になんて思ってないよ。きっと捨て駒にするつもりだよ。そうに決まってる。そんな奴らの言うことなんか、聞く必要ないって」
「⋯⋯」
同期は俯いた。
「誰に指示されたか教えてよ」
同期は、黙ったまま唇を引き結んだ。
「ルリスは怒ってないって言ってるよ。いつも一緒にいるから分かるけど、あれは本当に怒ってないよ。重症じゃないし、数日で完治するらしいし。だから、指示した奴について教えて」
同期は俯いたまま微動だにしなかったが、やがて首を横に振った。と同時に、デスクの上に水滴が落ちた。涙のようだ。同期は、声を絞り出すように言った。
「だから、だから、『全ての活動を今すぐにやめろ』って警告したのに⋯⋯やめてくれてたら、こんなことしなくて済んだのに⋯⋯」
「それって、レグルスに置かれてた紙の文章⋯⋯あれって君がやったの?」
同期は小さく首を横に振った。
「違う。言えないけど、それは違う」
「私たち、35日っていう企業に目をつけられているみたいなんだけど、その関係者から指示されたの?」
同期の目が再び泳いだのが分かった。やはり図星だと考えていいだろう。それからもいくつか質問してみたが、同期はほとんど何も話さなかった。プレトは自分に命令書が届いたときのことを思い出し、
「家族が人質に取られているの?」
と訊いてみた。同期の目元から溢れた涙が、再びデスクに落ちた。なるほど、脅されているのか。ルリスを傷付けたことは許せないが、置かれている境遇には同情した。
「私みたいにパラライトアルミニウムに沈められるかもしれないから、あまり一人で出歩かないほうがいいよ」
最後にそれだけ伝えた。静かに話を聞いていたチユリさんが、「また連絡するわね」と言い、ビデオ通話は終了した。
リビングに移動すると、ルリスは手の甲でモルモットを撫でていた。
「話せたの? 何だか顔色が悪いけど⋯⋯」
「話したよ。ほとんど何も喋ってくれなかったけれど、あいつの仕業でほぼ間違いないね。まだ推測の域を出ないけど、脅されて命令されたっぽい」
「そっか⋯⋯一緒に活動できると思って嬉しかったんだけどな」
ルリスの声が弱々しい。ため息をつきながら、プレトはソファに腰かけた。気分が悪い。されたことについても気分が悪いが⋯⋯攻撃があっさりバレたと指示役に知られたら、あの同期はどうなるのだろう。プライベートでの付き合いはないが、研究所では割と親しくしていたと思う。共同で研究したときは楽しかった。当時を思い出すと、現在との差に落ち込むしかなかった。気分が悪い、後味が悪い、胸くそが悪い。口の中が酸っぱくなった。
「なんなのあいつ、ごまかすの下手なくせに⋯⋯強情っぱりめ」
一人ごちると、ソファに身体を横たえた。ひどく疲れた。
「うげっ」
ソファから転げ落ちて目が覚めた。
打った肩をさすりながら上体を起こすと、見たことのない空間が目の前にあった。上も下も、右も左も、螺鈿のように輝きながら揺らめいている。その空間に、自宅で使っているソファがぽつんと置かれていた。振り返ると、ドリンクバーがあった。
「いつもの幻か……」
「そうだよ」
再び振り返ると、少女がすぐ後ろにいた。手渡されたコップには液体が入っている。それを一口飲んだ。
「なんだろう、これ。甘い香りがするけど⋯⋯頭文字はHだよね?」
「ヘーゼルナッツだよ」
「前回のグレープの方が断然、美味しかったな」
「わたしもそう思う」
プレトと少女は顔を見合わせて笑った。笑いつつも、プレトは山積みになった問題で頭の中がいっぱいになっていた。ふと、口を開いた。
「君が別れ際にいつも言っていた35日だけど、隣国の国営企業だったんだね」
「そうみたいだね。わたしも知らなかったよ」
「知らなかったの?」
「うん」
「じゃあ、『飲まないでね』っていうのは?」
「さあ⋯⋯」
少女は困ったように首を傾げた。本当に知らないようだ。
「どうして毎回言ってたの」
「どうしてだろうね。言ったほうがいい気がしたの」
「⋯⋯そっか」
これ以上、35日について聞くのは諦め、話題を変えることにした。
「前回会ったときにさ、ドリンクバーの後ろに赤い手形がついてたよね」
「拭き取ったから、今はないよ」
「ありがとう⋯⋯自分がサタンに酷い目に遭わされるんだって思っていたけれど、ルリスがケガしちゃった。これはサタンのせい?」
「サタンと、サタンに利用された人間のせいかな」
「だよね。ルリスを一人で行かせたの、後悔してるんだ。やっぱり私もついていけばよかった。でも、ついていったところで防げなかっただろうし。けど、私が先に機内に入っていれば何か違ったのかなって。だけど、行ったらまた捕まったかもしれないし。ちょっと自分でもなに言ってるか分からなくなってきた」
「⋯⋯」
少女は、丸い瞳でプレトのことをじっと見詰めている。好きに話していいと促してくれている気がした。
「同期だって、こんなことするような人じゃなかったはずだし、あの場に私がいたら何か違っていたのかもしれないなって」
「⋯⋯」
「チユリさんもショックを受けていたし」
「⋯⋯」
「とにかく、動揺してる」
「プレトお姉さんのせいじゃないよ。もちろん、ルリスお姉さんのせいでもないし。今みたいに弱っていると、サタンが近寄ってくるよ」
「え、やだ」
「どうしたらいいのか、お姉さんは知っているはずだよ」
「祈るんだっけ⋯⋯そうだ、私がドクププに刺されたとき、ルリスは一晩中祈ってくれたんだ。今度は私がそうすればいいのか。祈ったら早く治るかな?」
「治るよ」
「よし、祈るぞ。もしかして、私がサタンにつけ込まれないように励ましに来てくれたの?」
プレトの質問に答える代わりに、少女はにこりと微笑んだ。
「うげっ」
ソファから転げ落ちて目が覚めた。これで二度目だ。
「ねえ、大丈夫?」
ルリスが駆け寄ってきた。
「なんともない。寝ぼけちゃった」
「プレトまでケガしたら大変だよ。寝るならベッドで寝たほうがいいよ」
「いや、仮眠したら頭がスッキリした」
時計を確認すると、15分ほどしか経っていなかった。もっと長く少女と話していたような気がする。
「ならいいけど」
「手の調子はどう?」
「特に変わりはないよ。薬のおかげで、悪くはなっていない気がする。でも、いつ治るかな。治るまで、ムーンマシュマロ作りとか梱包とか、上手くできないかも。ああいう作業、好きなんだけどな」
「ルリスの手が早く治るように祈るね。ルリスは私のためにいっぱい祈ってくれたもんね」
「うん? まあそうだね。プレトが祈ってくれるなら早く治る気がするよ」
ルリスは木漏れ日のような明るい笑みを浮かべた。
(第89話につづく)

コメントを書く